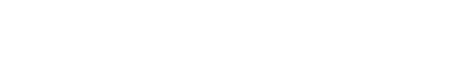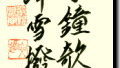紅炉上一点雪 (碧巌録)
紅炉上(こうろじょう)の一点の雪
「荊棘林(けいきょくりん)を透る衲僧家、紅炉上の一点の雪の如し」と碧巌録の南泉一円相の垂示の項にあり。荊棘林とはいばらの林のことであるが、人生はいばらの道に例えられ、道を行くに困難ないばらの林があり、また野獣、毒蛇、毒虫にも襲われよう。修行の道はなお険しいことである。ここでいういばらとは煩悩、妄想ばかりか悟ったとか大安心を得たとかの捉われのいばらである。

その煩悩、執着のいばらの林を透りぬけて来た禅の僧ならば、真紅に炎を上げて燃えさかる鉱炉の上に一片の雪が舞い落ちたとしてもシュンともいう間もなく、すぐに消えてしまだろう。
このように真の禅者の境涯というものは、あらゆる事象にとらわれることもなければ、こだわり引きずることはないというのが、「紅炉上一点雪」の語である。苦しい困難な修行の道を透過してきたからこそ得られる境地であるともいえる。
昔の我が小学校には教室に石炭ストーブが置かれていて、凍てつく朝は鋳鉄のストーブが真っ赤になるまで燃やして暖をとってから授業が始まった。いたずらっ子たちは先生にしかられながら、よく雪の小玉や氷の破片をストーブの上にのぜてジュッと音を立てて溶けて消えるのを楽しんだものだ。
真っ赤に燃えさかる高炉に雪は落ちても瞬時に消えてしまい何の跡形も残したりはしない。このように禅者の活発発地、活き活きとした正念の働き、燃えるような熱い求道心があれば、どんな妄念、妄想の雪はたちまちのうちに消えてなくなり、跡形も残すことはなく、迷いの入り込み余地もないことである。
この場合の「紅炉上一点雪」は煩悩の世界を超脱した禅者に言うことばであるが、我々凡人が味わうことばとしては、もっと身近なものとして使いたいし味わうことも出来るのではないだろうか。
当寺は毎週木曜日の夜に座禅会をやっている。何の指導も策励もせず、ただ勝手に集まってきて三炷を共にするだけに過ぎない。
一回きりの単なる座禅体験だけの人もいれば、何年も何年も通い続ける人もいて常時十数名が山寺の閑寂を味わっている。

座禅をはじめたばかりの人は座禅によって無心になろう、無心になれると思うのか「雑念ばかりで無心になれません」という。そんな時「何十年も座禅会をしている私も居眠りばかりで一度だって無心になれていません」といって煙に巻いている。それは座禅をして無心になろう、悟りを得ようというのも煩悩であり、何かを期待し過大の何かを求めようなどというのも欲である。
しかし、たとえ煩悩が起きようが、それに引きずられて二念、三念を起こし妄念妄想にかられず受け流すことができるかである。ここに「紅炉上一点雪」の語のように、しっかりとした菩提心、求道心を燃やし維持してさえおれば、必然的に迷妄は消滅していくことだろう。